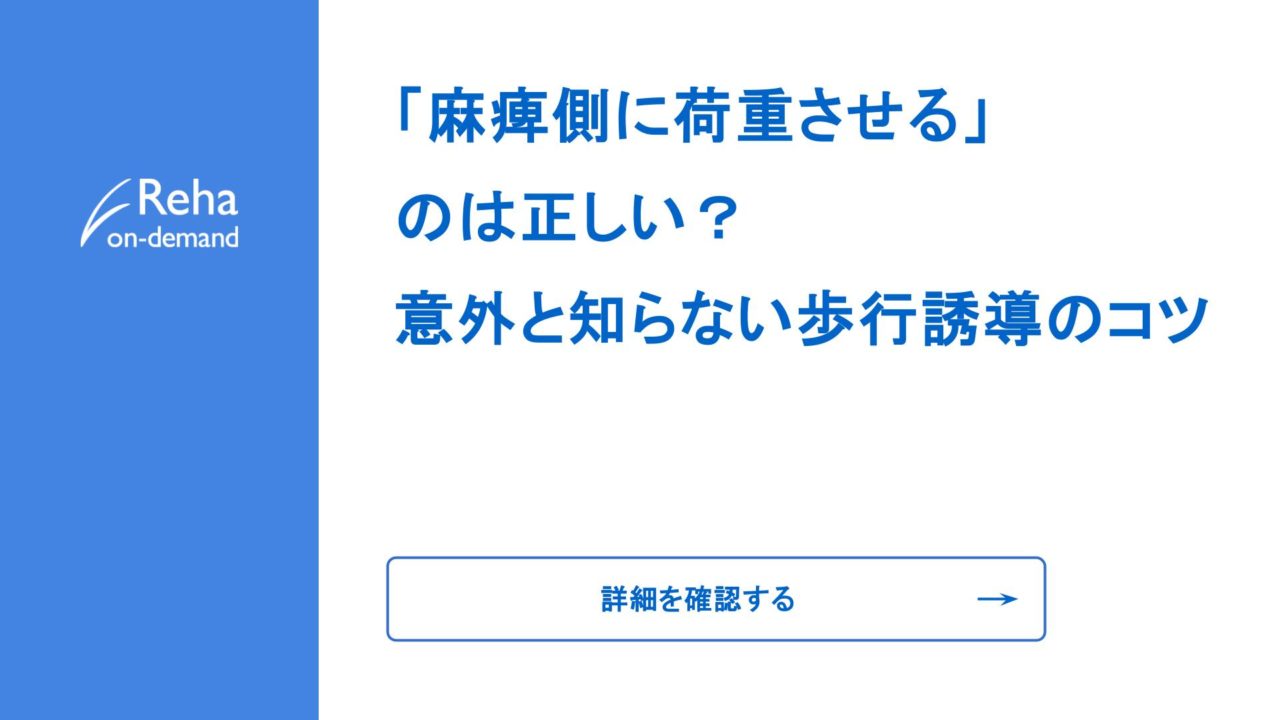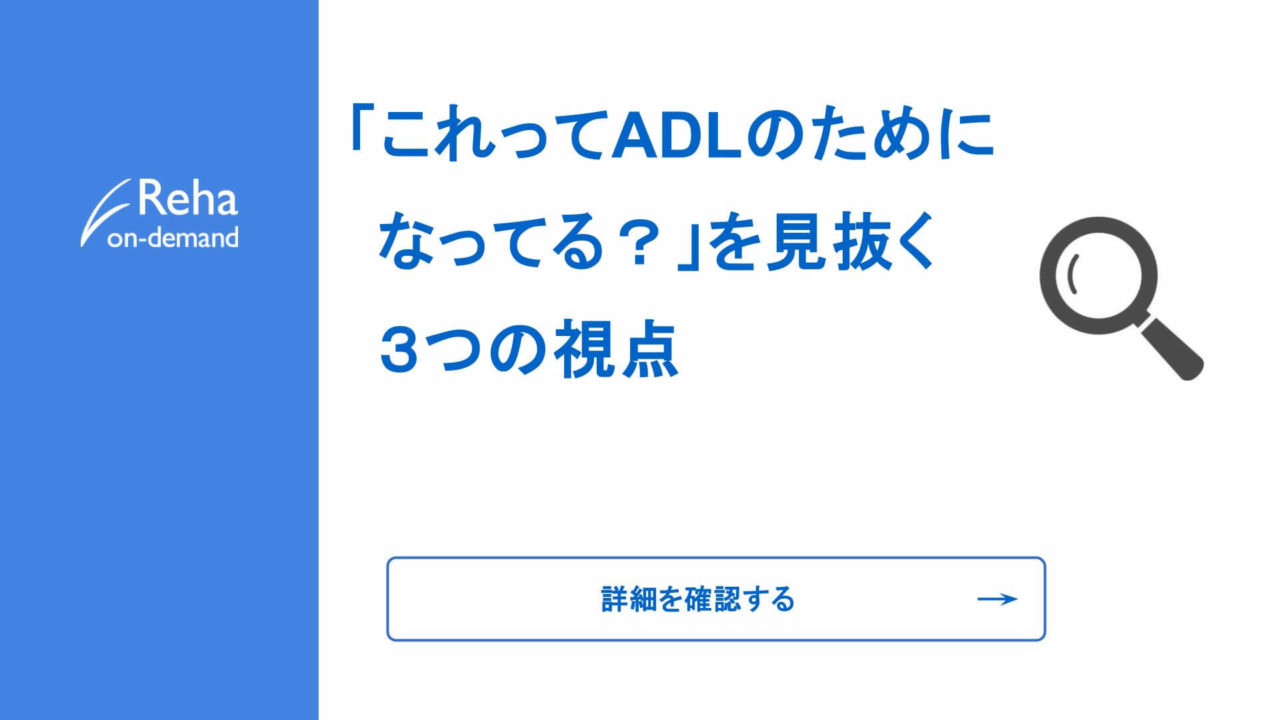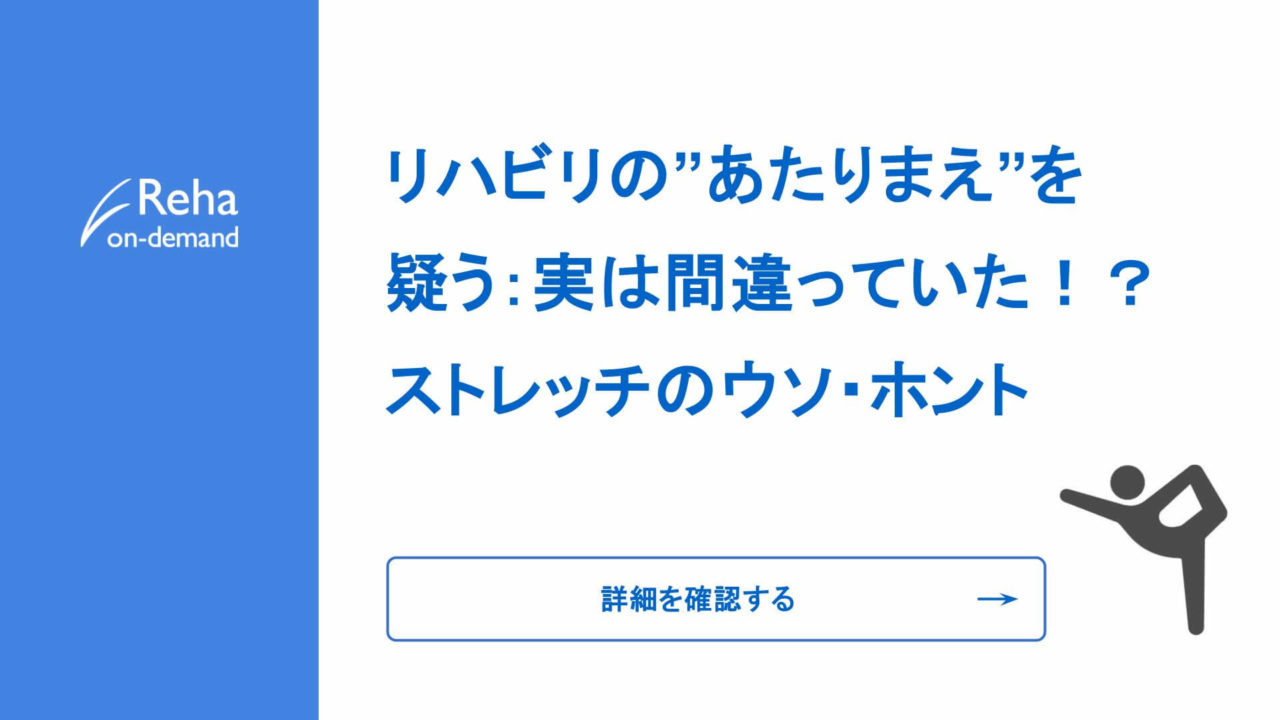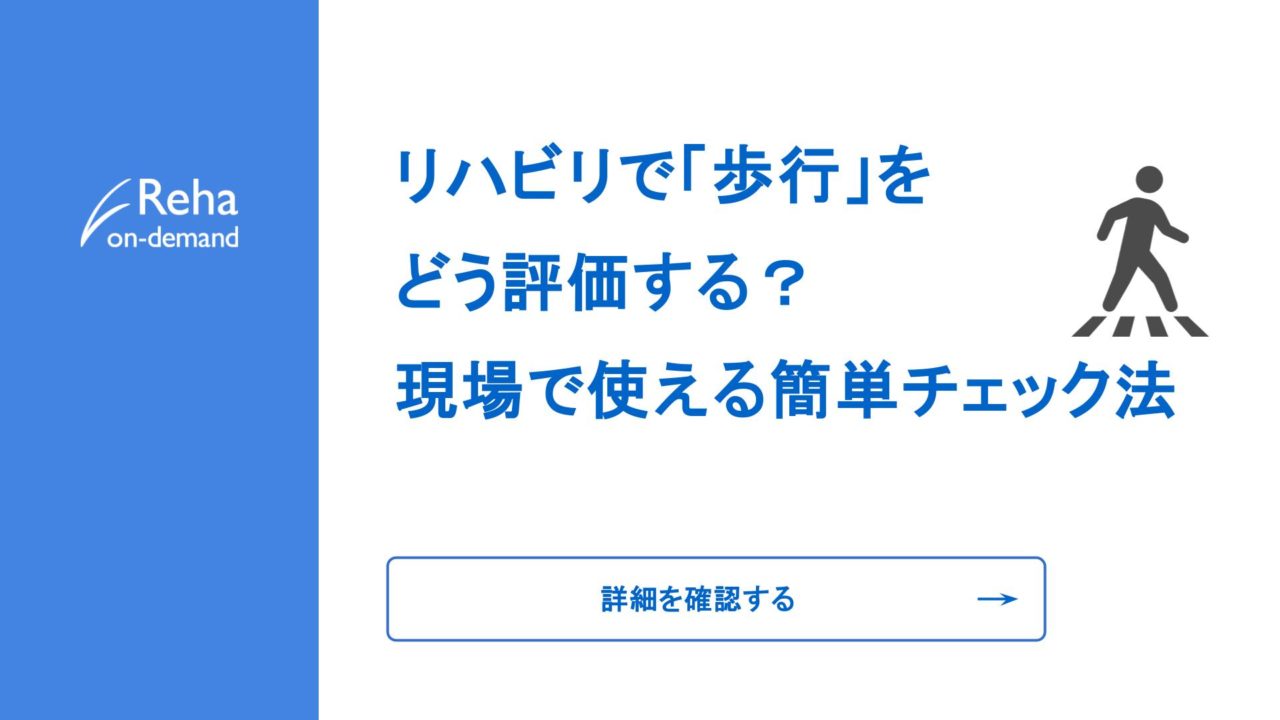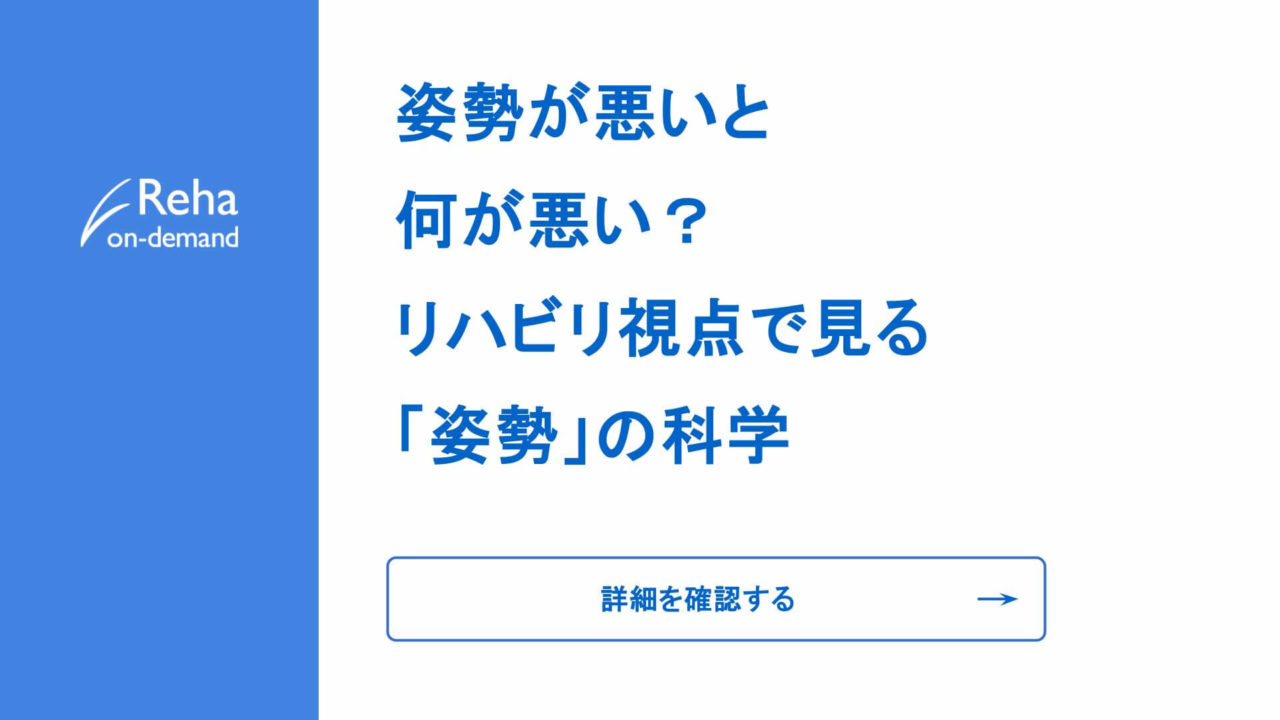ADL、ICF 、目標設定|2026.1.9|最終更新:2026.1.9|理学療法士が執筆・監修しています
序文
リハ場面で一生懸命エクササイズを組んでいると、ふと
「これって本当にADLのためになってる?」
と不安になること、ありませんか。
筋力や可動域は確かに大事ですが、「良い訓練っぽい」ことと「実際の生活が変わること」はイコールではありません。実際、麻痺上肢の機能回復スコアが改善しても、日常生活での腕の使い方とは必ずしも強く結びつかない、という報告もあります。
この記事では、明日から自分の介入を見直せるように、「これってADLのためになってる?」を見抜く3つの視点を整理します。
視点①:ICFで「活動・参加」までつながるストーリーが描けているか
まず押さえておきたいのは、「機能がよくなればADLも勝手によくなるわけではない」という事実です。脳卒中後の上肢リハでは、運動機能のスコア改善と、実際の生活での麻痺側上肢の使用頻度が弱い関連しか示されないという研究があります[1]。
さらに、運動機能の改善がQOLに影響するのは、「腕をどれだけ日常生活で使うか」「ADLがどれだけ自立するか」を介した“間接的な経路”である、という解析も報告されています[2]。
つまり、機能 → ADL → QOL というストーリーを意識して組まないと、「機能だけ良くなった」で終わる可能性が高いわけです。
①-1 ICFのどこを狙っている介入かを言語化する
ICFで言うと、
- 機能・構造(筋力、ROM、協調性…)
- 活動(更衣、トイレ動作、歩行、洗面…)
- 参加(家事役割、仕事復帰、趣味活動…)
のどこを直接ターゲットにしているか、そしてそこから上位レベルへの“橋”をどう渡すのかを、言葉で説明できるかがポイントです。
チェック用のテンプレート:「この○○訓練によって△△という機能を高め、その結果、□□というADLが、◇◇という生活場面でやりやすくなることを狙っている。」
この一文がスラスラ出てこない介入は、「ADLのため」と言い切るにはまだ曖昧かもしれません。
①-2 ゴール設定が“機能どまり”になっていないか
実際のストロークリハの現場では、ゴール設定が「握力アップ」「歩行速度アップ」など、機能・能力レベルに偏りがちであることが指摘されています[3][4]。
一方、クライエント中心のADL介入では、「自分の今の生活状況を理解しながら、どの活動を取り戻したいか」を一緒に考えるプロセスが、主体的な参加につながることが報告されています[5]。
若手療法士としては、
- 「この訓練の最終ゴールは、患者さんのどんな“活動・参加”か?」
- 「そのゴールは本人が“やりたいこと”として語っているか?」
を毎回確認してみてください。
視点②:訓練タスクの“現実らしさ”をチェックする
2つ目の視点は、「その訓練タスクがどれだけ現実の生活に似ているか」です。
上肢リハの研究では、タスク指向型・活動ベースの訓練が、上肢機能やADL改善に有効であることが系統的レビューで示されています[6]。
また、在宅でのリハプログラムは、病院中心のケアと比べて、ADL自立や活動頻度、バランスへの自信などで長期的なメリットを示した報告もあります[8]。
②-1 「検査でできる」と「日常でやっている」は別物
歩行能力の研究では、施設内での歩行テストの成績と、実際の日常生活でどれだけ歩いているかが必ずしも一致しないことが示されています[7]。
これは「テストとしての歩行」と「生活としての歩行」が別物であることを意味します。
リハのタスクも同じで、
- ベッドサイドでの段差昇降 → 現実の玄関・階段昇降
- 室内での平地歩行 → スーパーでの歩行・方向転換・カゴ操作
といったように、環境や同時課題が変わると難易度も意味合いも変わります。
②-2 自分の介入を“現実らしさ”で採点してみる
今やっているメニューを、以下の軸で確認してみて下さい。
環境の近さ
★1:病室内だけ、日常環境とはかなり違う
★2:病棟内の廊下や階段など、やや近い
★3:自宅・模擬キッチン・模擬玄関など、かなり近い
タスクの意味づけ
★1:単なる運動課題(例:乗り降りのないスクワット
★2:ADLの一部分を切り出した課題(例:立ち座りだけ)
★3:実際のADLとして完結した課題(例:トイレ動作を一連で)
複雑さ・同時課題
★1:単独動作のみ
★2:2つの動作を組み合わせる
★3:注意分割・物品操作・会話なども含んだ、現実に近い状況
合計が低いメニューは、「ADLのため」と言いつつ、実は“検査っぽい訓練”にとどまっている可能性があります。
視点③:ADLを動かすのは「筋力」だけじゃない―行動・心理面まで含めて考える
3つ目の視点は、本人の行動パターンや心理状態まで含めて、ADLへの影響を考えられているかです。
高齢者では、自己効力感(「自分ならできる」という感覚)とADL能力の関係を調べた研究で、自己効力感とADLの関係の多くが「動機づけ(やる気)」に媒介されていることが示されています[9]。
また、転倒への恐怖や転倒関連の自己効力感は、ADLや身体・社会的機能と関連し、「怖いからやらない」という回避行動を通じてADLを制限しうることが報告されています[10]。
③-1 「できる能力」と「やっている現実」のギャップを見る
- 筋力もバランスも改善している
- テストでも十分なスコアが出ている
- でも、家では相変わらずベッド上中心の生活
という患者さん、思い当たりませんか?
この場合、
- 「怖い」「疲れそう」「失敗したくない」
- 「家族に迷惑をかけたくない」
といった感情がブレーキになっている可能性があります。
③-2 介入に「心理・行動のスイッチ」を組み込む
ADLのための介入と胸を張って言うには、少なくとも以下のどれかは入れておきたいところです:
小さな成功体験を積ませる工夫
例:ほんの数メートルの歩行+即フィードバック、「さっきより早く歩けましたね!」
恐怖の対象に段階的に慣らす
例:見守りありでのトイレ歩行 → 手すりを使っての一人トイレ → 夜間トイレ…と段階づけ
「どこまでなら自分でやってみたいか」を一緒に決める
例:転倒リスクを評価した上で、「ここまでは自分でチャレンジしてみる」というルール作り
筋力訓練そのものも大事ですが、「本人がそれを日常生活で使ってみようと思えるか?」という心理的ハードルを下げる工夫が入っているかどうかで、ADLへの波及効果は大きく変わります。
おわりに
「これってADLのためになってる?」というモヤモヤは、若手療法士だからこそ感じられる大事な感覚だと思います。
- 視点①:ICF上のどのレベルまでストーリーが描けているか
- 視点②:タスクや環境がどれだけ現実の生活に近いか
- 視点③:行動・心理面のスイッチまで含めて設計できているか
この3つのチェックポイントを、明日の自分のプログラムに当てはめてみてください。全部を一気に変える必要はなく、「今日は1つのメニューだけ、ADLとのつながりを言語化してみよう」くらいの小さな一歩で十分です。
その一歩が、「なんとなく良さそうな訓練」から「確かにADLのためと言える介入」への大きな違いを生んでいきます。