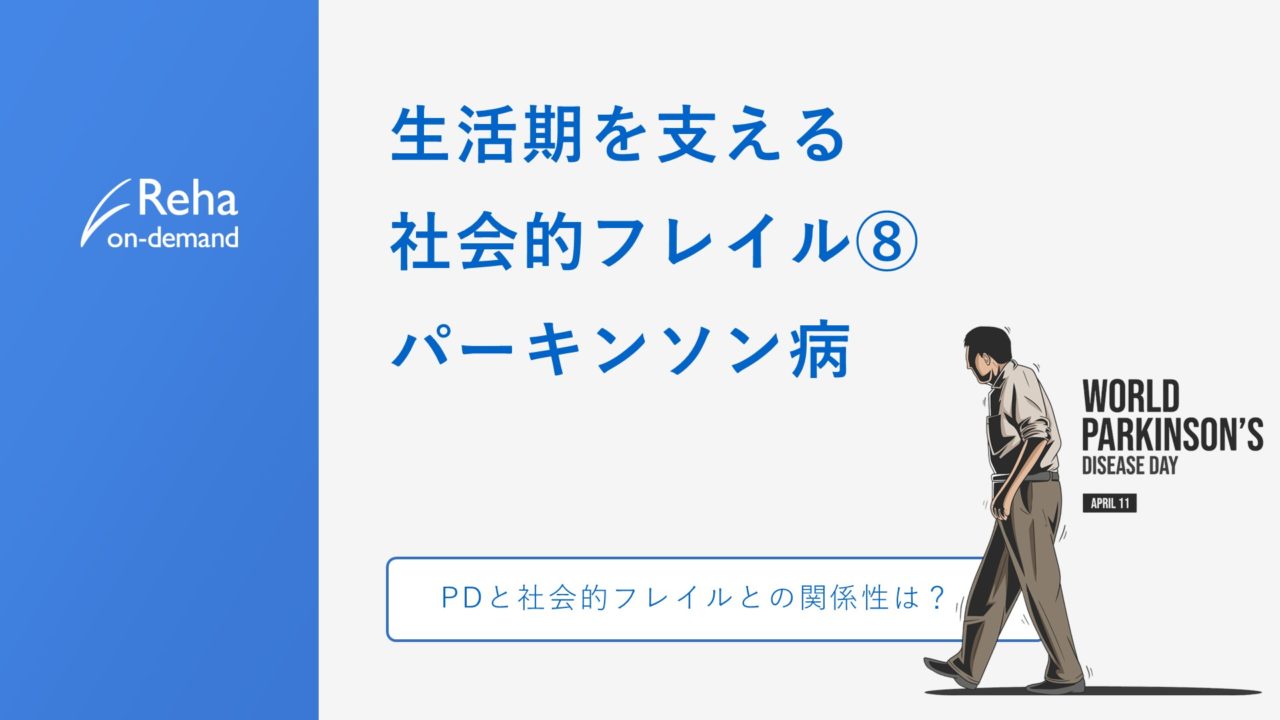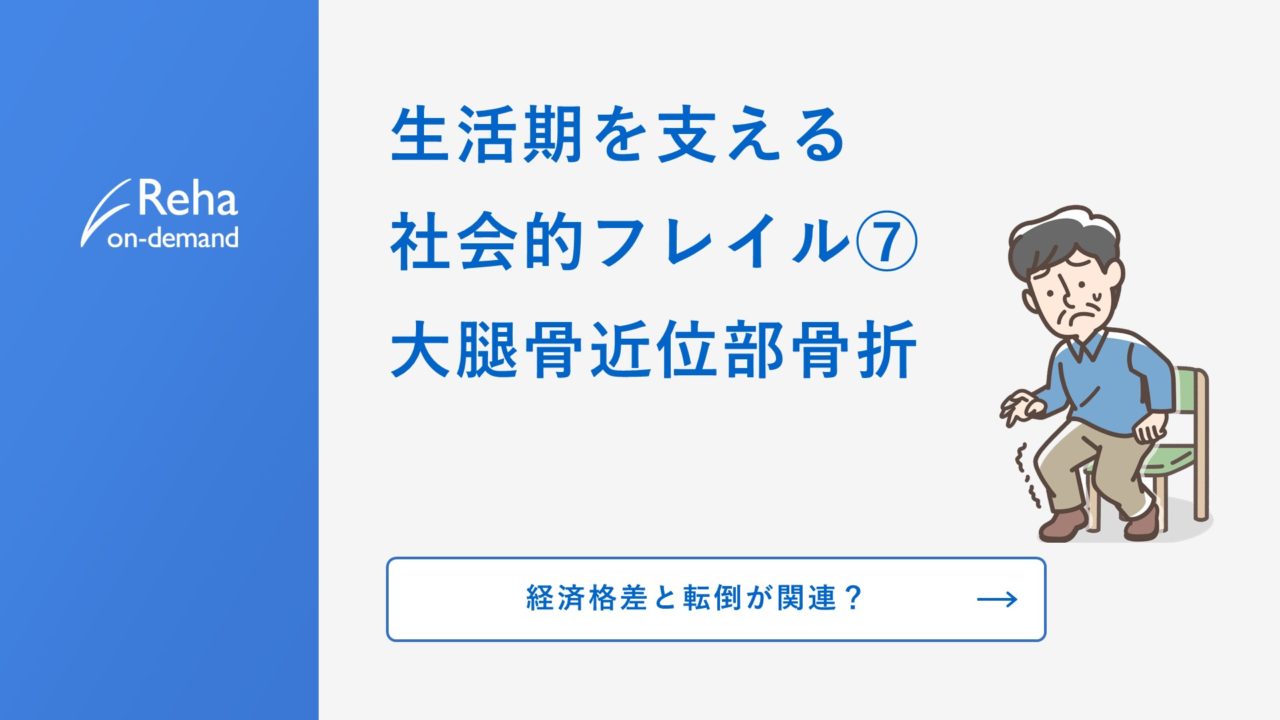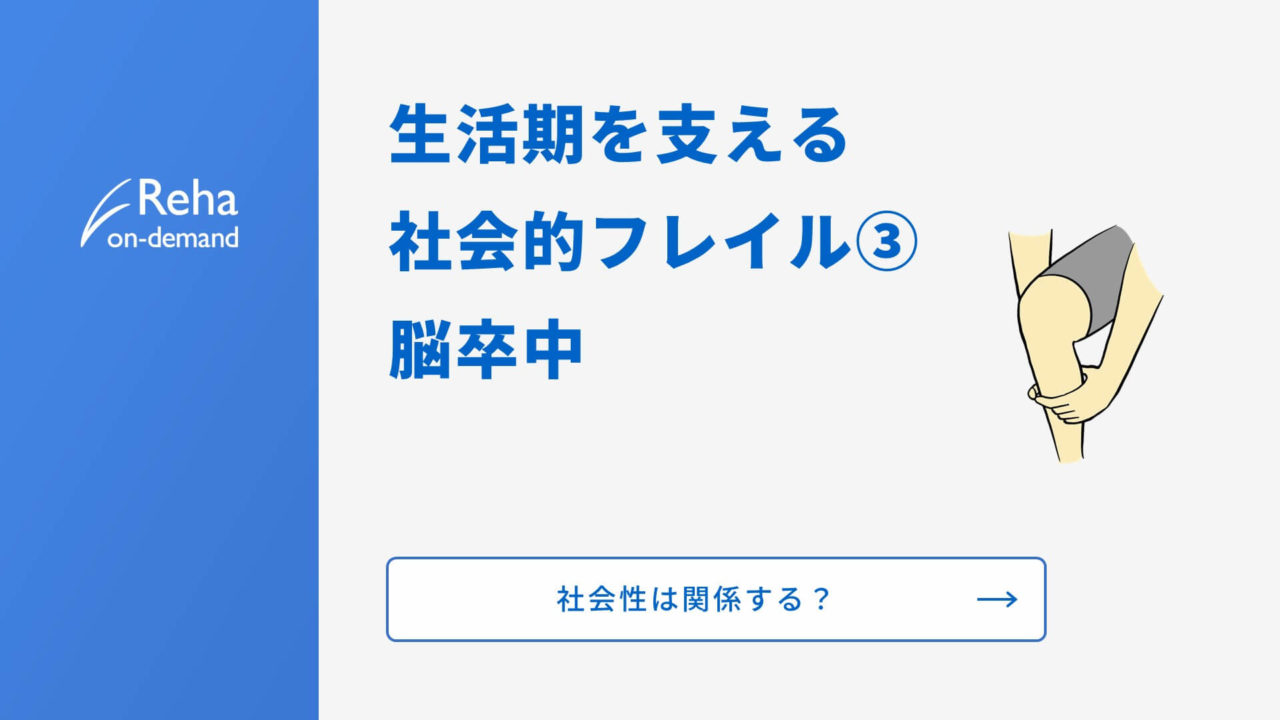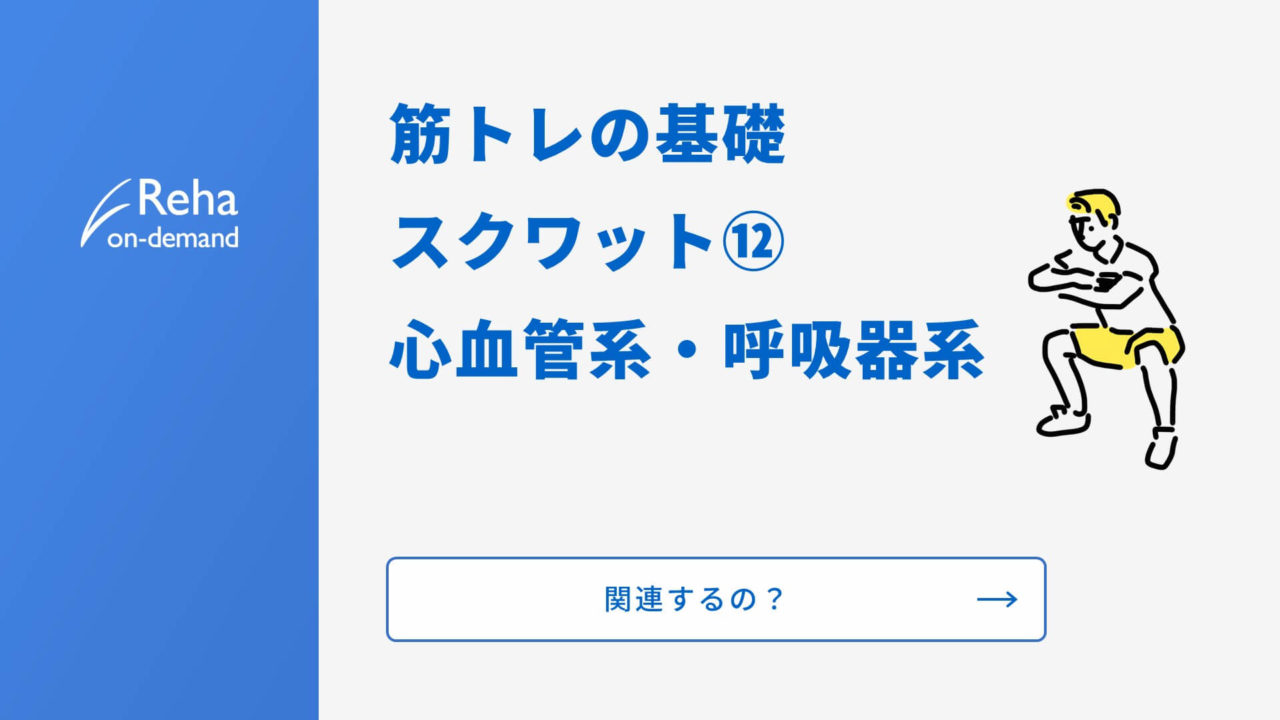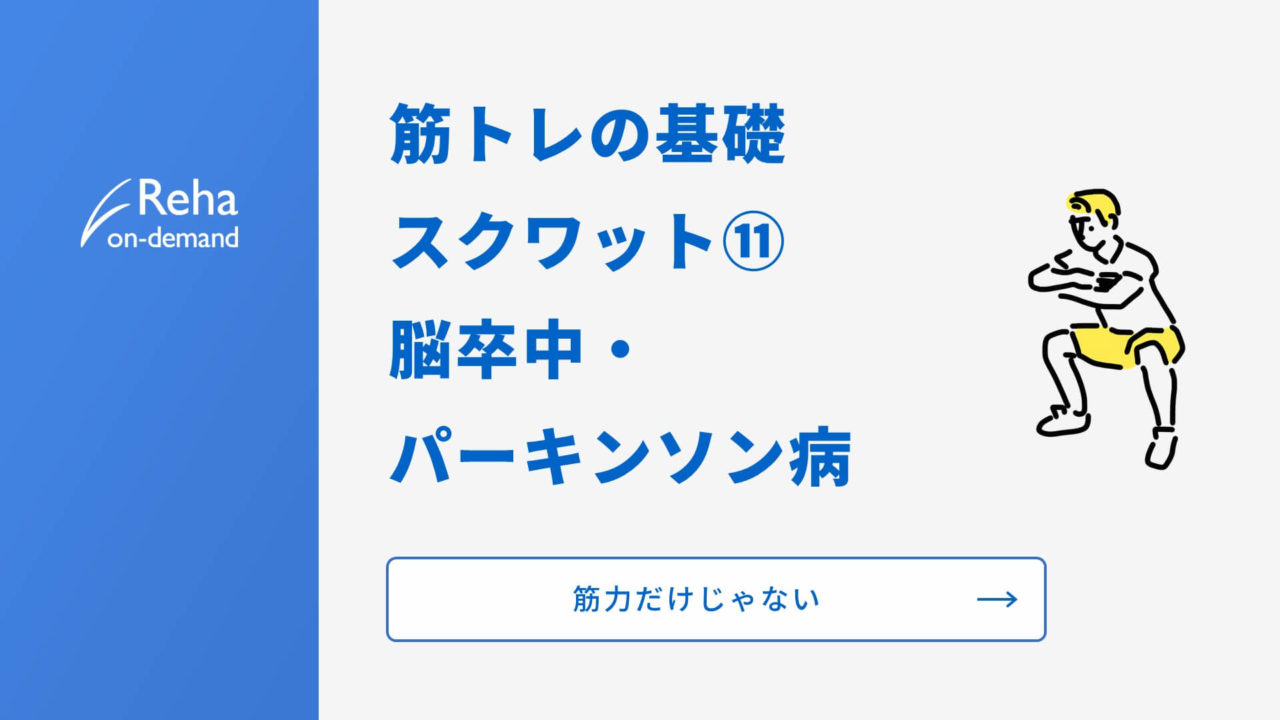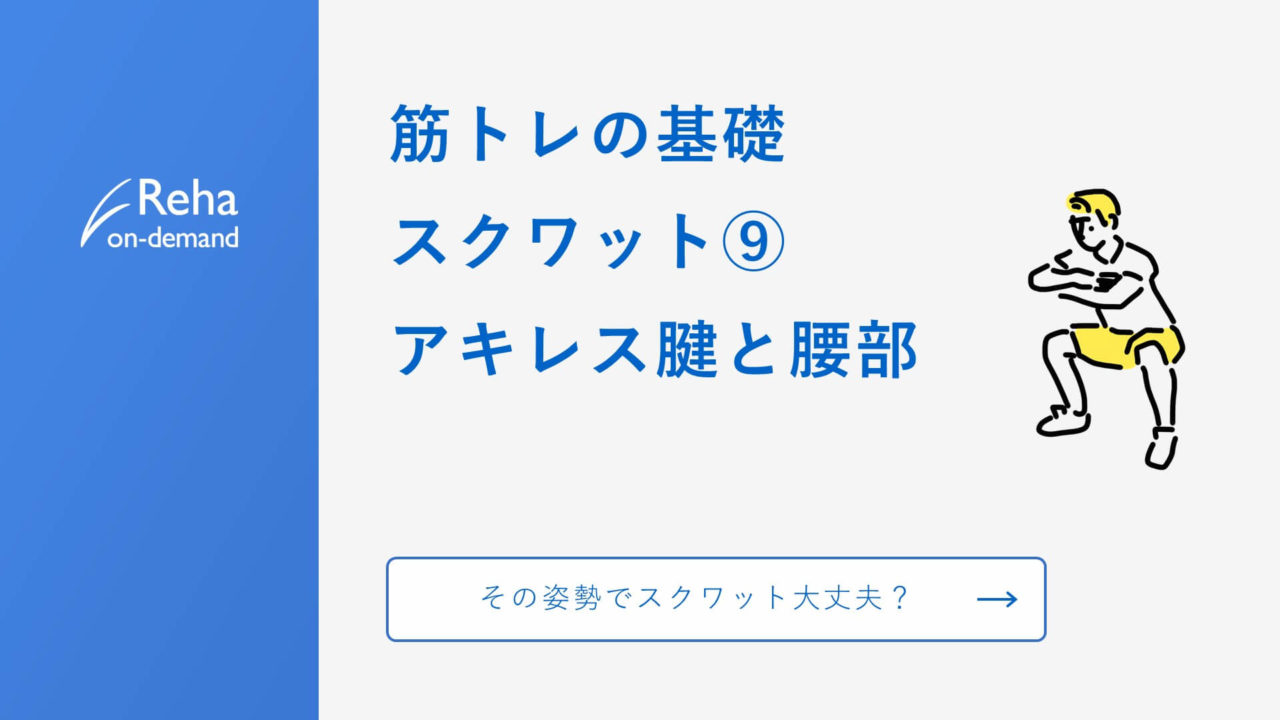[no_toc]
食事観察、先行期、準備期|2022.2.24|最終更新:2022.2.24|理学療法士が執筆・監修しています
序文
前回までは、摂食嚥下に関連する構造や機能について、理学療法士の視点で知っておくべき項目をみてきました。今回からは、摂食嚥下の過程の各期において、理学療法士の視点での観察ポイントについてみていきたいと思います。
|
✅ 「食べる」行動には覚醒状態が重要 ✅ 食べ物や食具が認識できないと、食べる行動に移せない ✅ 食べている途中も姿勢に注意 |
先行期
先行期は認知期とも呼ばれ、食べ物を認識し、口に運ぶまでの過程です。この時期は覚醒状態や上肢・体幹機能などが関係しているため、理学療法士による評価、介入も重要な時期です。確認するポイントとしては、
- 覚醒状態や注意機能が正常に働いているか
- 食べ物を食べ物として認識できているか
- 食具を適切に使用できるか、
- 食べ物の形状や形質を認識できているか、
- 食物を口に運ぶことができるか、
- 食具を操作している時に姿勢が崩れないか
などが挙げられます。
覚醒状態が不十分な状態であれば、食物の認知が行えません。また、食べようとしても、食べるために必要な運動のプログラミングが適切に作動できないため、動作を遂行することができません。さらに、覚醒の中枢である脳幹網様体は姿勢調整の働きもあるため、食べようとして上肢を動かそうとすれば、姿勢調整が行えないことで姿勢が崩れてしまいます。姿勢が安定しなければ上肢操作が難しくなるため、食具を使用して食物を口まで運ぶことが難しくなります。まずは覚醒を促す介入を行うことが大切です。
注意機能も食べるために大切な機能です。認知症や頭部外傷後の方で、目の前の食べ物に集中できず、食事が進まないというケースを経験したことがある方は少なくないのではないでしょうか?注意機能が低下していると、食べるという動作を持続して行うことが難しくなります。周囲からの視覚情報や聴覚情報など、注意が逸れてしまう因子をできるだけ取り除く環境調整を行うことが必要です。
認知機能障害や視覚障害、レビー小体型認知症のような幻視を伴う疾患に罹患していると、食べ物を食べ物として認識することが難しくなります。認知症の方が食べ物を弄んだり、幻視が見えてしまう方がふりかけや食器の模様を虫と認識してしまい、食べることができなくなるという場面を経験したことがある方もいらっしゃるかと思います。その方が食べ物をどう認識しているのかを確認し、食べ物として認識できるようにする工夫を行うことが大切です。
食具を使用できるかどうかも、食べる行動には重要です。観念失行など高次脳機能障害によって道具を適切に使用することができない、上肢・手指の機能障害によって食具の操作が行えないといったことがあると、食べ物を口まで運ぶことができません。高次脳機能障害によって食具の操作が行えない場合には、おにぎりやサンドイッチなど、食具を用いずに手で食べられるような食事内容にするといった工夫が有効な場合があります。また、上肢・手指の機能障害が原因であれば、機能障害を改善するための理学療法を行うことや、低下している機能を補うことができる自助具を選定することが必要です。
食べ物の形状や形質を認識することも、安全に食べるために大切です。食べようとしている物の形、硬さ、重さ、熱さなどの特徴がわからなければ、食べ物を操作する際にうまく取れなかったり、口まで運ぶ際に取りこぼしてしまったりしてしまいます。また、口に入れる際には、液体であれば啜るように口唇の形状を変化させなければいけませんし、硬い物であれば、切歯ではなく臼歯で噛める位置に運ぶ必要があります。認識能力が低下している方に対しては、安定して安全に食べることができる食形態を検討し、調整することが必要かもしれません。
覚醒状態、食物認知、上肢機能、道具の使用が良好でも、食事動作中に姿勢が保持できなければ、安全に食べることはできません。土台となる体幹を上肢の動きに合わせて安定させることができるかは、大切なポイントです。上肢操作中に姿勢が崩れてしまえば、食べ物を口に入れることが難しくなります。また、口まで運べても、姿勢が崩れたままでは咀嚼や嚥下が正常に行えないため、誤嚥の危険性が高くなります。椅子やテーブル、クッションなどを調整し、姿勢保持が行えるようにポジショニングを行うことが大切です。
準備期(口腔準備期)
準備期は食べ物を口腔内に取り込み、咀嚼をして食塊を形成する時期です。この時期に観察するポイントとしては、
- 食べ物を口腔内に入れる際に、ちゃんと開口することができるか。
- 口腔内に入れた後に、こぼれないように閉口することができるか。
- 咀嚼が適切に行えているか。
- 口腔内に感覚異常が生じていないか。
などが挙げられます。
顎関節の動きに制限がある場合には、開口範囲が狭くなり、口に入れられる食べ物の大きさや形状に制限が生じます。また、高齢者に多い円背姿勢では、顎を突き出した姿勢になってしまうため、下顎の動きに制限が生じ、開口範囲が狭くなります。一口量が多いことは誤嚥リスクを高めますが、少なすぎても、食事に時間がかかってしまうため、食事中の疲労感につながってしまい、結果として食事量が減ってしまう原因になり得ます。STさんや歯科の先生に相談し、改善策を考えることが大切です。
口に取り込む時や咀嚼している時に口を閉じたままにしていられないと、食べこぼしが多くなり、実際に食べた量は減ってしまいます。脳血管障害の片麻痺や種々の原因による顔面神経麻痺などでは、口唇を閉鎖することに作用する筋が麻痺してしまうため、口腔内に食べ物を保持しておくことができなくなってしまいます。また、パーキンソン病などで不随意運動がある場合にも、閉口保持が難しくなります。食後にエプロンや衣類に食物が多く付着している場合には、食事摂取記録よりも実際の食事摂取量が少ない可能性があることを念頭に置いておく必要があります。
咀嚼運動は以前説明したように、単純な上下運動だけではなく、前後左右の動きや舌との協調的な動きが必要です。また、咀嚼回数が必要以上に多くなっていないかも確認が必要です。ずっと同じ位置で咀嚼している場合には、元々のクセも考えられますが、他の部位に咀嚼時痛が生じていたり、噛み合わせが悪くなっていたりする場合もありますので、歯科の先生やSTさんに相談する必要があります。また、咀嚼回数が異常に多い場合には、唾液分泌量が少なく、食塊が形成できない、舌機能が低下していて送り込めない、認知機能や感覚機能が低下していることで口腔内の食物認知能力が低下しているなどが考えられます。理学療法士ではその鑑別は難しいため、こちらも歯科の先生やSTさんに相談することが大切です。
おわりに
今回は摂食嚥下の過程の先行期と準備器についてみてきました。細かくみていくと、理学療法士が関われるところもありますので、歯科の先生やSTさんと連携して介入することで、より効果的な関わりが行えるかもしれません。
本記事の執筆・監修・編集者
✅記事執筆者(宇野先生)のTwitterはこちら↓↓
地域在住高齢者では、70分/回×週2回×16週間の運動介入を行うと、プレフレイルの46%、フレイルの50%がそれぞれロバストやプレフレイルまで改善したそうです。https://t.co/E0fiqzFPr7
— Isao Uno(宇野勲)@リハ栄養学会2023実行委員長 (@isao_reha_nutri) June 2, 2022
関連する記事
✅ 前回記事はこちら
✅ 栄養に関する人気記事はこちら
あなたにおすすめの記事
参考文献
[1] 日本摂食嚥下リハビリテーション学会、eラーニングテキスト